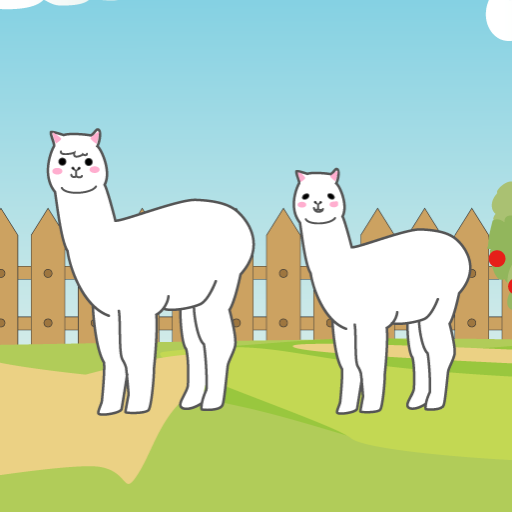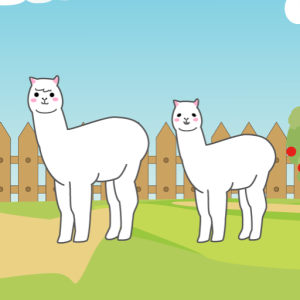我が子が何でも怖がる場合、その子供たちと上手に向き合う方法について考えてみましょう。たとえば我が家は、6歳と4歳の2人の息子たちがおり、どちらもビビりな性格です。
上の子は跳び箱や逆上がり、担任の先生に怒られることなど、さまざまなことが怖いようです。下の子も大きな恐竜のディスプレイや知らないおばちゃんに声をかけられることなどで同じくらい怖がります。
このような怖がりな子供たちに対して、親が心配になることもあるでしょう。将来に支障が出るのではないか、心配になることも理解できます。
しかし、多くの場合、子供たちが怖がることは成長過程であり、問題ではありません。特に小学校低学年ぐらいまでは、怖がりな子供が多いものです。
これは生物学的な側面も考慮すると自然なことであり、自分を守るために未知のものやイレギュラーな状況に対して怖がることが本能的な反応です。

子供が怖がる多くの場合は全く問題なく、むしろその時期はそれぐらいの方が丁度よいです。
子ども、とくに小学校低学年ぐらいまではむしろ怖がりな子供の方が多いくらいです。
これは生物学的にも正しいことなんですよ。
自分で身を守る力が備わっていない子どもは、自分にとってイレギュラーなことや物に対して怖がり、回避しようとします。
人間に限らず動物の本能とでも言いましょうか。
そして最初は怖かったものでも、これは自分にとって危険ではないものだと納得すれば、子ども特有の好奇心が勝り自分からコンタクトを自然と取るようになります。
このように子どもの思考を理解した上で、親が教えてあげることは本当に危険なものと、そうでないものの線引きです。
一つ一つの、子どものビビりアクションを見ておいてあげることが大事です。

あとは、子どもがいろんなことに怖がってしまうことに対して、必要以上に怒らないことです。
子どもからすると、
怖いものに出くわした!
怖いな~と思っている時に、
怖がってどうするの!とママに怒られた!
ママも怖い!
ってな感じ。
そう、怖いのダブルパンチを喰らってるようなもんなんですねー。
そしてその行為は、下手すれば子供にとって一生のトラウマになってしまう場合もあるんですよ。
あなたも、子どもの頃のメッチャ怖かった体験、未だに憶えてたりしませんか?
過去の自分の怖かった体験を思い出してみれば、強烈な恐怖は長く残るものです。
このぐらいのことでビビってんじゃねぇ!とかあんまりお子様には言わない方が良いですよー。
却ってビビってしまうスイッチになってしまい、より怖がりになってしまう子や、
怖がってはいけないと、感情を我慢し過ぎてしまう子になってしまうリスクにつながります。
子供は怖がりながら学びます。
その学びの芽を親が摘んでしまうのではなく、怖くなくなったことを、また怖くなくなったことで出来るようになったことを目一杯褒めてあげましょう。
その方がお子様は勿論、我々親の心も体も健康的に成長していきます。そう思いませんか?
子供たちの怖がりをサポートする方法
- 積極的な挑戦を提案する: 子供たちが少しずつ怖いものに挑戦する機会を提供しましょう。小さな成功体験が自信につながり、怖がりを克服する一歩となります。
- 興味を引く話や絵本を共有する: 怖いと感じるテーマに関する興味深い話や絵本を通じて、子供たちの好奇心を引き出しましょう。物事を別の視点から見ることで、怖さが和らぐことがあります。
- 共感と理解を示す: 子供たちが怖がる状況に理解を示し、共感することが重要です。彼らの感情を受け入れ、一緒に感じることで安心感が生まれます。
- 怖いものに対してポジティブな体験を創り出す: 子供たちに怖いものと向き合い、その克服を通じてポジティブな体験を提供しましょう。成功体験は成長に繋がります。
親の役割
- 耐 patience 強くなる: 子供たちが怖がることに対して、焦らず耐え強く接することが大切です。焦りが感じられると、子供たちも余計に不安になります。
- コミュニケーションを大切にする: 子供たちとのコミュニケーションを深め、怖がりの原因や感じ方について話すことが重要です。オープンで安心できる雰囲気を作りましょう。
- 学びと成長を褒める: 怖がりを克服した際には、子供たちの努力や成長を褒めてあげましょう。肯定的なフィードバックは自信の基盤となります。
- プロフェッショナルの協力を得る: 必要であれば、子供たちの怖がりに関する専門家や学校のカウンセラーなど、プロフェッショナルの協力を得ることも検討しましょう。
子供たちの怖がりは、彼らが成長し、新しい経験を通じて学ぶための自然なプロセスの一部です。親はサポートと理解を通じて、子供たちが健康的に成長する手助けをすることができます。